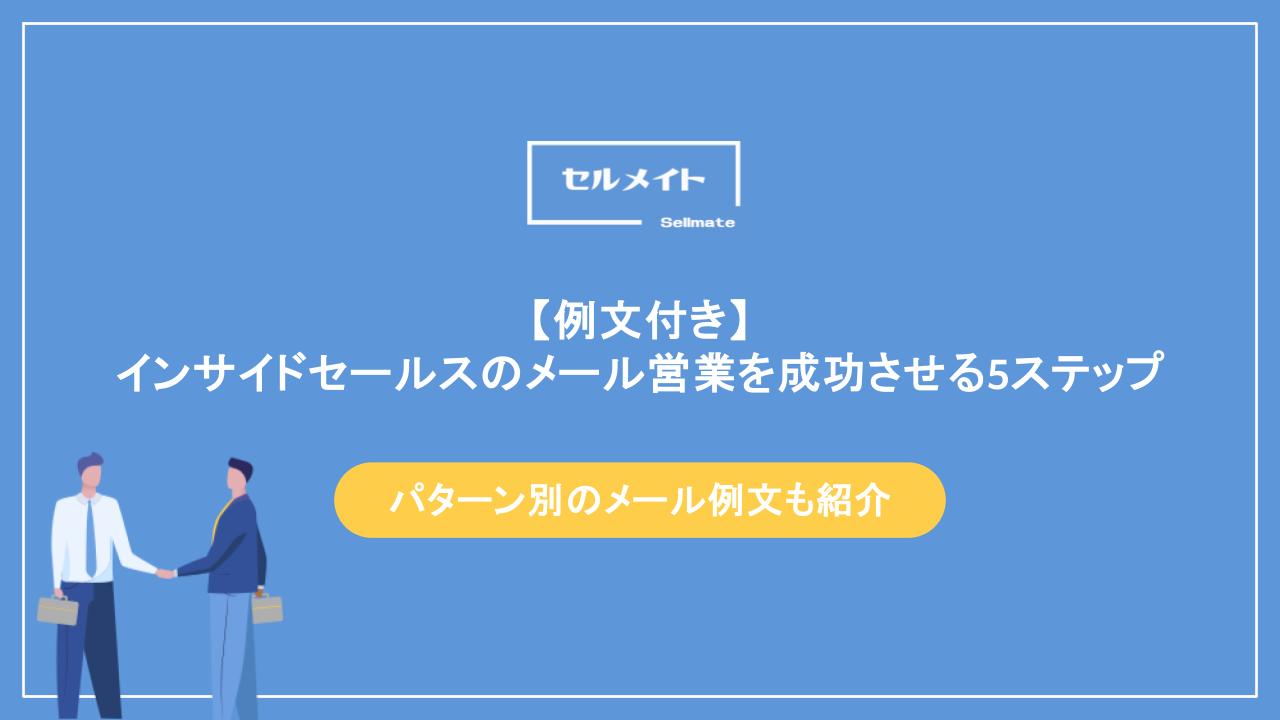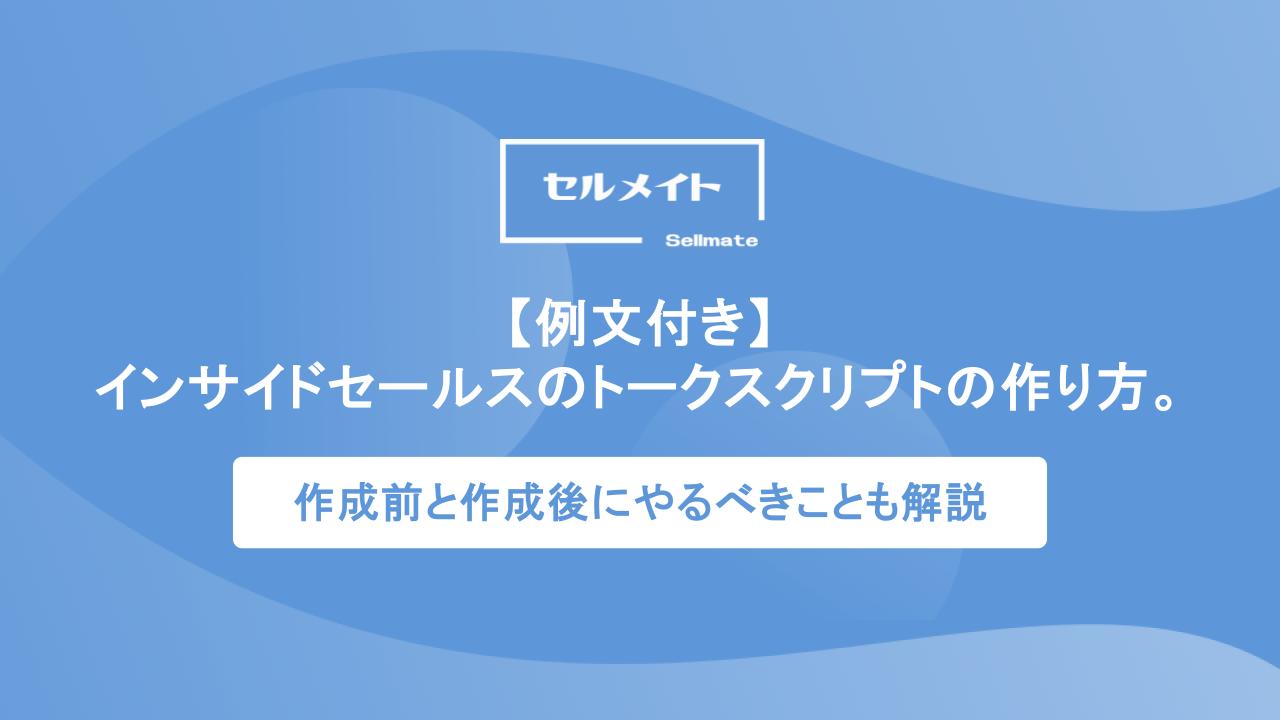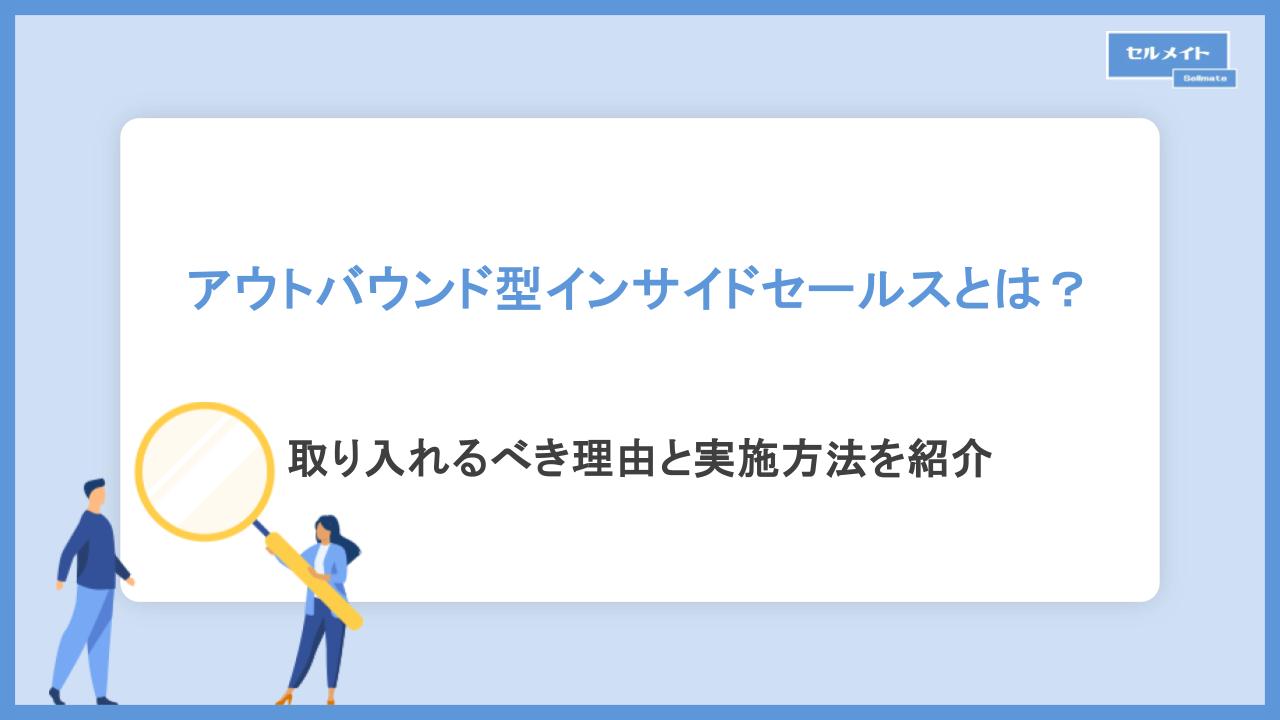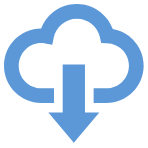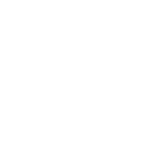インバウンドセールスとインサイドセールスの違いとは?メリットも紹介
2025/7/28

「インバウンドセールスとインサイドセールスはどのように違うのか」
「自社に向いているのはインバウンドセールスとインサイドセールスのどっち?」
近年、顧客自ら情報を収集して購買行動に移行するインバウンドセールスが注目を集めています。一方で、営業手法の一つであるインサイドセールスはインバウンドセールスと表現が似ているため、上記のような疑問をもつ方も増えてきています。
本記事では、インバウンドセールスとインサイドセールスの概要と違いについて解説します。それぞれのメリットや向いている企業の特徴もご紹介しますので、営業活動や見込み顧客へのアプローチ方法にお悩みの方は参考にしてください。
目次
インバウンドセールスとインサイドセールス
類似する表現であるインバウンドセールスと、インサイドセールスは、そもそもどのようなことを意味するのでしょうか。ここではそれぞれの概要を解説します。
インバウンドセールスとは
インバウンドセールスとは、Webサイトや展示会、各種広告などを通じて自社の商品やサービスをアピールし、興味を持って問い合わせや資料請求をしてきた見込み顧客に対して購入を促す営業手法のことです。
近年、インターネットの普及により購買行動が変化し、見込み客自身が積極的に情報収集を行うようになったため、インバウンドセールスは営業活動において重要な役割を果たします。
「インバウンド」とは「外から中へ」という意味で、相手からの興味・関心を高めて、商品・サービスへの問い合わせを引き出すことが重要です。
インサイドセールスとは
インサイドセールスとは、主に電話やメール、ツールなどを活用して行う営業手法です。インバウンドセールスもインサイドセールスもどちらも営業手法ではあるものの、見込み顧客へのアプローチ方法や過程が異なります。
一般的なインサイドセールスは非対面で行われる営業活動であり、オフィス内で電話などで見込み顧客とコミュニケーションを定期的に取ることで関係を構築し、見込み顧客を育成するのが特徴です。
インバウンドセールスとインサイドセールスの違い
インバウンドセールスとインサイドセールスの主な違いは、営業活動の起点と手法です。
インバウンドセールスにおける起点は、顧客側であり、見込み顧客からの自発的な問い合わせや興味・関心に対応する形で営業活動を展開します。一方、インサイドセールスは、企業側から見込み顧客に対してアプローチを行い、非対面で関係性を深めていく手法です。
インバウンドセールスの一環として、インサイドセールスが活用される関係性にあります。
インバウンドセールスのメリット
インバウンドセールスは顧客起点で営業活動が展開されるため、企業にとってさまざまなメリットが生じます。ここでは、代表的なメリットをご紹介します。
成約につながりやすい
従来行われていた、飛び込み営業やDM(ダイレクトメール送付)などのアウトバウンド営業では、興味のない顧客に対してアプローチを行うため断られるケースが多く、成約率が低くなる傾向にありました。
一方、インバウンドセールスでは、すでに興味・関心が高まっている見込み顧客に対して営業活動を行うため、無駄な営業活動を減らしながら、高い成約率を維持することができます。営業活動の効率化が期待できるのもメリットです。
営業担当者の負担を軽減できる
インバウンドセールスでは、顧客が自らが企業に対して問い合わせを行うため、営業担当者が新規開拓のために無作為にアプローチする必要がありません。
従来の営業活動では、飛び込み営業やコールドコールを行い、顧客の関心を引く努力が必要でした。しかし、インバウンドセールスでは、すでに興味・関心が高まった状態の見込み顧客に対応すれば良いため、営業担当者は従来に比べてより少ない労力で商談に進めることができます。
マーケティングと連携しやすい
インバウンドセールスはマーケティングと連携して、より多くの見込み顧客を獲得できるのもメリットです。
例えば、企業の公式サイトやブログ、ホワイトペーパー、ウェビナーなどのマーケティング施策を通じて価値ある情報を提供し、見込み客の興味・関心を引き付けることができれば、問い合わせの増加につながります。
問い合わせは、見込み顧客の購買意欲が高まったタイミングで行われるため、ニーズに応じた最適な提案によって効果的なクロージングが可能となります。
企業の信頼性やブランド力を向上させやすい
インバウンドセールスでは、見込み顧客は企業の発信する情報に基づいて良し悪しを判断するため、企業の信頼性やブランド力の向上に役立ちます。
例えば、業界の専門知識を活かしたブログ記事や動画コンテンツを発信することで、見込み顧客に対して「この企業なら信頼できる」と感じさせられます。このような信頼できる価値のある情報をさらに提供し続けることで、見込み顧客は企業に愛着を抱くようになるため、ファン化させることも可能です。
インサイドセールスのメリット
インサイドセールスにも、さまざまなメリットがあります。ここでは3つのメリットを紹介します。
営業コストを削減できる
インサイドセールスは、従来のアウトバウンド営業と比べてコストを大幅に削減できるのもメリットです。
一般的な営業活動では、移動費や宿泊費、電話代などのコストが発生します。しかしインバウンドセールスではこれらのコストがほとんどかかりません。
また、公式サイトへの問い合わせやホワイトペーパーのダウンロードなど、オンライン上での集客や商談が主体となるため、物理的な移動を伴う営業活動を減らすことができます。
短期間で多くの顧客にアプローチできる
インサイドセールスでは、デジタルツールを活用することで、短期間で多くの顧客に接触できます。
例えば、WebマーケティングやSNS、メールマーケティングを実施すれば、一度に数千人規模の見込み顧客に情報を届けることが可能です。
従来のアウトバウンド型の訪問営業や電話営業では、1日に対応できる顧客数に限界がありました。一方、インバウンドセールスなら24時間365日、顧客との接点を持ち続けることができます。
見込み顧客の育成(リードナーチャリング)がしやすい
インサイドセールスでは、見込み顧客が自ら情報収集を行うため、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)を効率的に行えます。
特に、マーケティングを自動化、効率化できるMAツール(マーケティングオートメーションツール)を活用すれば、顧客の行動履歴に応じた情報を適切なタイミングで発信できるようになります。このように、無理な営業をせずとも、自然な形で顧客を商談へと導くことができるのもメリットです。
データを活用して効率的な営業を実現できる
データ分析を活用することで、より効率的な営業活動を実現できるのもインバウンドセールスのメリットです。
例えば、Webサイトのアクセス解析やCRMを活用すると、顧客がどのWebページを閲覧し、どのコンテンツに興味を持っているのかを把握できます。つまり、顧客の抱える課題やニーズ、興味関心をデータから判断可能です。
これらのデータをもとに営業戦略を最適化すれば、顧客の購買意欲が高まるタイミングを見極められ、より確実に成約へと導くことが可能です。
インバウンドセールスが向いている企業
自社にインバウンドセールスが向いているかどうかは、取り扱う商材やビジネスの性質によって判断可能です。ここでは、インバウンドセールスが向いている企業の特徴をご紹介します。
消費者向けの商品を提供する企業
近年の消費者行動において、消費者は商品・サービスの購入前にインターネットで情報収集を行うことが一般的です。特に、検索エンジンやSNSを通じて情報を積極的に探す傾向が見られています。
そのため、企業側は、自社の商品に関連するキーワードでコンテンツを作成して検索結果で上位表示されるようにSEO対策を行えば、潜在顧客を効率的に自社サイトへ誘導できます。
また、SNSを活用して商品の魅力や使用感を視覚的に伝えることで、顧客の購買意欲を高めることも可能です。
コンテンツマーケティングを活用する企業
コンテンツマーケティングにおいて、企業が発信するコンテンツは顧客にとって有益な情報源となります。ブログ記事や動画コンテンツを通じて顧客の興味関心を引きつけられれば、自社への信頼感を醸成できるでしょう。
さらに、定期的にコンテンツを提供し続けることで、購買意欲をより高めることも可能です。また、ホワイトペーパーや事例紹介などの専門的なコンテンツを公開すれば、より深い知識や情報を求める顧客層にもアプローチが可能です。
日常的に購入される商品を提供する企業
日常的に購入される商品は消費者にとって身近な存在であり、定期的な情報提供やキャンペーンを通じて、顧客の購買意欲を維持しやすいのが特徴です。例えば、メールマガジンやWebサイトのコラム、SNSなどで新商品情報やセール情報を定期的に配信することで、顧客の購買行動を促せます。
また、顧客からのレビューや質問に対して丁寧に回答することで、顧客満足度を高められ、リピート購入につなげられます。
インサイドセールスが向いている企業
ここからは、インサイドセールスが向いている企業の特徴を解説します。
B2Bビジネスを展開する企業
B2Bの購買プロセスは、担当者だけでなく上司など複数人が関わり、契約には稟議などの手続きを必要とします。そのため、購買プロセスが複雑で時間がかかることが多く、購買意欲を保持してもらうための顧客との密なコミュニケーションが不可欠です。
インサイドセールスでは継続的なコミュニケーションを通じて長期的に信頼関係を構築でき、顧客の課題やニーズを深く理解できるのが特徴です。また、顧客の購買プロセスに合わせて適切な情報提供や提案を行えば、効率的に成約につなげられます。
製品やサービスが高額な企業
高額な製品やサービスの購入は、顧客にとって慎重な検討が必要であり、担当者との信頼関係が重要です。
例えば、不動産や金融商品、企業の基幹システムなどの、顧客の意思決定に時間がかかる商材を扱う企業にとって、インサイドセールスは顧客との関係構築と成約率向上に貢献できる手段となります。
また、インサイドセールスは定期的かつ個別的で密なコミュニケーションを通じて、顧客の疑問や不安を解消できるため、商材が高額な企業に向いています。
顧客と長期的な関係を持つことになる企業
インサイドセールスは継続的なコミュニケーションを通じて、顧客の課題やニーズを深く理解し、的確にサポートできる営業手法であり、顧客との長期的な関係が想定される企業にとって最適です。
また、顧客からのフィードバックを収集して製品やサービスの改善に役立てることで、顧客満足度を高めて長期的な関係構築へとつなげられます。特に、SaaS商材やサブスクリプション型のサービス、定期的なメンテナンスやアップデートが必要な製品を扱う企業にとって重要な営業手法となるでしょう。
インサイドセールスの成功事例
インサイドセールスの新規立ち上げや運用改善は成功事例を参考にするとスムーズに行えます。ここでは、インサイドセールスの運用に成功した3つの企業様の事例をご紹介します。
株式会社ワンキャリア
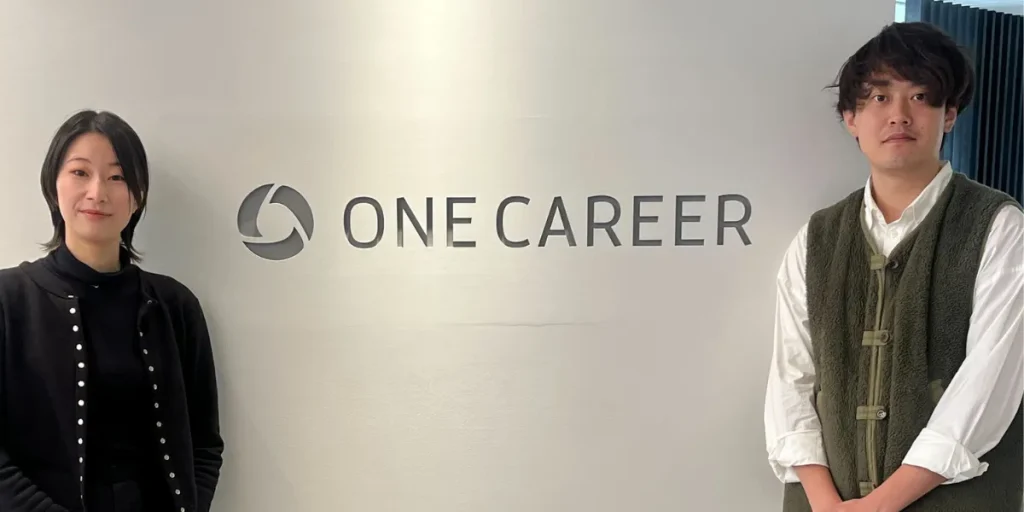
株式会社ワンキャリアでは、営業活動の効率化してリストを最大限に活用するために、インサイドセールスの代行サービス「セルメイト」の支援を導入しました。
就活サイトや転職サイトなどを提供している同社では、ターゲットリストが全体の法人数の10%に満たない状態が長期化しており、自社だけでは効果的なアプローチを起こせていませんでした。
「セルメイト」の導入後は、プロジェクトマネージャーによる施策の提案を受け、顧客の反応をもとにトークスクリプトを改善し、最適なコミュニケーションによる商談獲得率の向上に成功しています。
株式会社Rockets

株式会社Rocketsは、慢性的なリソース不足の解消や見込み顧客への継続的なアプローチを目的に、「セルメイト」を導入しました。
企業データべースを活用して営業活動を自動化できるSaaSプラットフォームの開発・運営を行う同社で課題となっていたのがリソース不足です。1万件以上のハウスリストに対して1名の担当者が対応しており、またリードナーチャリングも十分に行われていませんでした。
「セルメイト」によるインサイドセールスの支援を導入し、顧客体験に沿うシナリオにもとづいて潜在顧客向けたトークスクリプトを作成した結果、温度感の高い商談獲得に至ります。さらに、流入経路ごとの検証と施策の改善を迅速に行い、ハウスリストの掘り起こしからの受注獲得につながっています。
株式会社オムニサイエンス

株式会社オムニサイエンスでは、顧客紹介やセミナーといったオフラインでの顧客獲得に限界を感じ、アウトバウンド施策の導入を検討していました。そこで課題となっていたのが、社内におけるインサイドセールスの構築ノウハウやリソースの不足です。
「セルメイト」の導入後にアウトバウンドを実施した結果、ヒアリング精度を向上でき、質の高い商談が獲得できるようになりました。トスアップにより充実した情報を引き継ぐことで商談時の見込み客との認識齟齬も減少し、現在ではより効果的な営業活動を行っています。
SaaS企業のインサイドセールス導入ならセルメイト
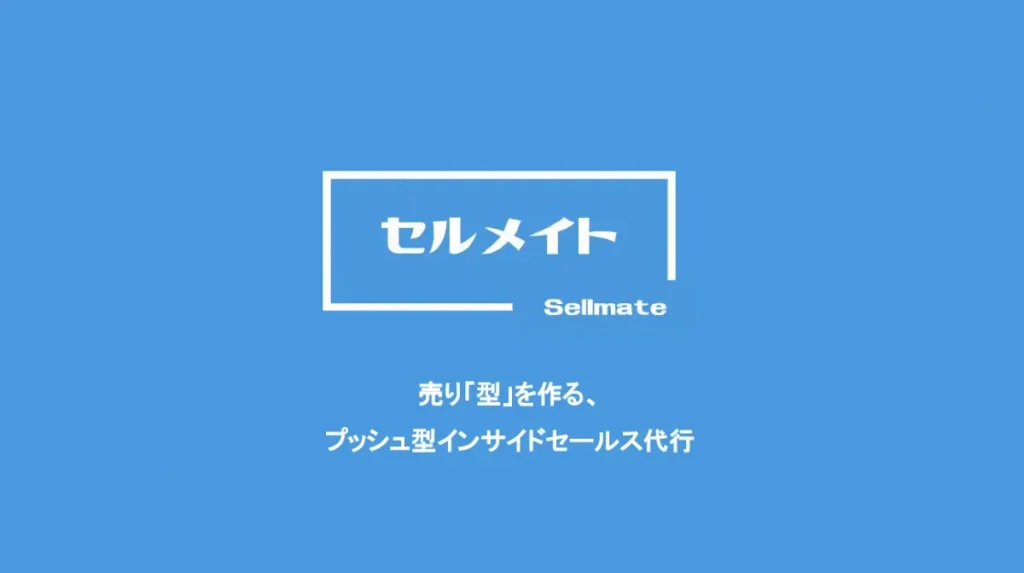
インバウンドセールスは、Webサイトや広告などから自発的に情報を収集して、問い合わせや資料請求に至った見込み顧客に対して商品・サービスの購入を促す営業手法です。一方、インサイドセールスは、主に電話やメールなどで非対面で行う営業手法です。
両社はともに営業手法の一つですが、インバウンドセールスの起点は顧客側にあるのに対して、インサイドセールスの起点は企業側である点で違います。
このような特性の違いから、インバウンドセールスは、消費者向けの商品提供やコンテンツマーケティングを実施している企業に向いているといえます。一方で、B2Bビジネスを展開している企業やSaaS製品やサブスクリプションサービスなど顧客との長期的な関係を持つビジネスでは、インサイドセールスが向いています。
インサイドセールスは、自社で内製化することで、外注よりもコストを抑えた実施が可能です。セルメイトでは、営業系SaaSサービスを提供していた実績とSaaS業界に向けたインサイドセールスの知見を活用した内製化の支援を実施しています。インサイドセールスの導入、内製化をお考えの方は、ぜひご相談ください。